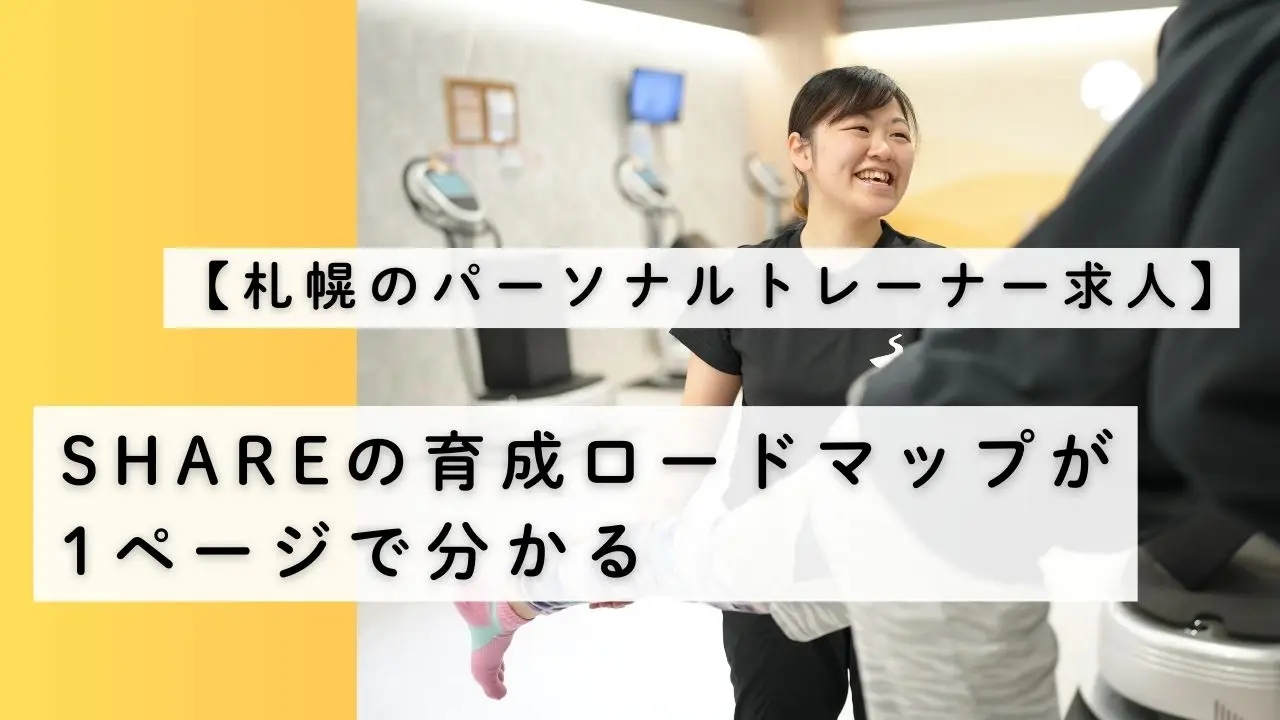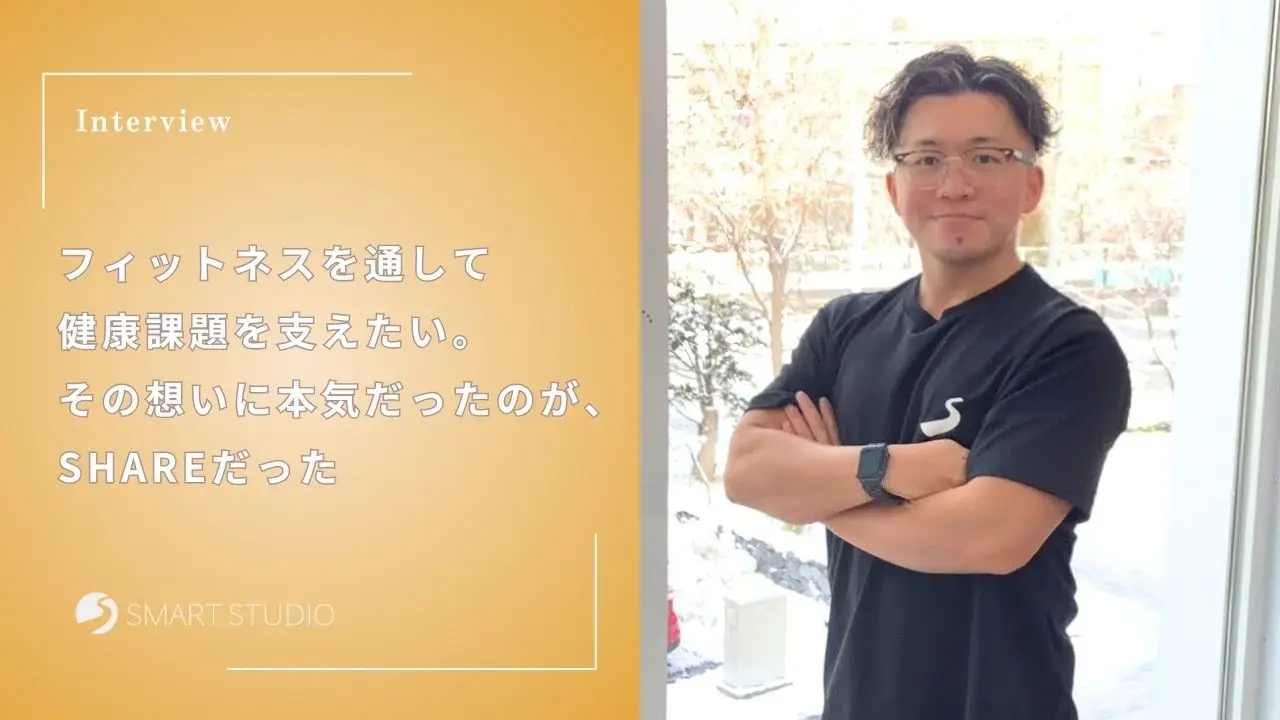地域とともに歩む、喜茂別町での介護予防事業

喜茂別町×SHARE
― 自然と共生する“予防ケア”モデルの挑戦 ―
豊かな森と羊蹄山を望む喜茂別町は、総人口1,957人・高齢化率38.5%という“超高齢化”のステージにあります。町内の医療機関は町立クリニックを含む診療所が1件のみで、専門治療を受けるには隣接市町村まで車で30〜40分かかるのが現状です。
こうした地域でこそ、**発症を未然に防ぎ、自立を長く保つ“予防的アプローチ”**が不可欠です。
SHAREのパーソナルトレーニングジムやリハビリ特化型デイサービス、自費リハビリ施設を運営し、培ったノウハウを活かし、町と協働で喜茂別町での介護予防事業を受託することになりました。
喜茂別町の健康課題
| 観点 | 現状データ | なぜ課題か |
|---|---|---|
| 高齢化率 | 39.7 %(2020 年)|全国平均 28.7 %より +11 pt | 要介護発生リスクが高い人口構造。フレイル・サルコペニア対策を早期から打つ必要がある。 |
| 生活習慣病 | 高血圧症 20.0 %/糖尿病 10.9 %(後志広域連合国保、治療中) | 服薬継続・運動療法の自己管理支援が不足し、重症化・医療費増大につながる。 |
| 特定健診受診率 | 39 %(令和 4 年度)|国の目標 60 %に届かず | 未受診層の掘り起こしが不可欠。早期発見の遅れが生活習慣病の重症化を招く。 |
| 医療・交通インフラ | 診療所 1 院のみ/公共交通はバス中心(冬季減便) | 「受診・運動したくても移動できない」こと自体がフレイル促進要因。 |
3つの地域特性が生む“複合バリア”
気候:積雪量 5 m 超の長い冬が屋外活動と移動意欲を低下させる
食文化:塩蔵・発酵食品中心で 高塩分摂取 が常態化
移動手段:自家用車非保有世帯は バス減便期に外出困難
これが示すこと
高齢化 × 生活習慣病 × インフラ制約 が重なり、町民の「健診も運動も続けにくい」構造的課題を生む
介入は “通年・多面的” であることが必須
例:屋内中心の筋力トレーニング+オンライン教室での運動機会を確保
例:管理栄養士による減塩支援と地元食品店とのコラボで塩分カット商品を普及
だからこそ SHARE は―
データ可視化 → 運動指導 → オンライン継続支援 という 3 ステップモデルで、
“移動のハードル” を越え、
暮らしの中に介護予防を埋め込む 仕組みづくりに挑戦しています。
事業の全体像
| フェーズ | 施策 |
|---|---|
| ①健康データの可視化 | 定期測定会で体組成・バランス・筋力などを取得。結果は検査結果として本人にお渡しし、自身が把握できるように。 |
| ②グループ運動教室 | 週1回/町民センターでSHAREの理学療法士、健康運動指導士、柔道整復師が指導。椅子体操+マット運動+立位トレーニングなど。 |
| ③オンラインサポート | 月2回のオンライン運動指導。 |
| ④町民向けイベントの開催 | 子供から大人まで参加しやすい町民向けイベントの開催。 |
参加者の変化のストーリー
70代のAさん
「冬は家の中で閉じこもりがちだったけれど、札幌から教室に来てくれるので嬉しい。」
70代のBさん
「運動するのはもちろん楽しいし、スタッフさんがとても専門的ですごくわかりやすい」
と笑顔で話してくれます。こうした小さな成功体験の積み重ねが、町全体の健康づくりを動かす原動力になります。
未来への展望
札幌だけでなく、道内の札幌以外の地域にお住まいの方々にも健康維持のためのサービスを届けることが、私たちの使命です。
今回の喜茂別町での取り組みを継続し、札幌から離れた地域に対しても健康をお届けすることが出来たらと考えています。
どんな地域に住んでいても、健康で活力ある生活を送れる環境を整えていくことが、私たちの目指すべき未来です。

引き続き皆様からのお声を頂けるよう、スタッフ一同すすんで参ります。

総合病院での臨床経験を経て、株式会社SHAREに入社し、医療・健康・介護福祉の共創に励んでいます。 私たちが地域の皆様のお役にどう立てるか? 自治体・医療機関・地域にお住まいの皆様のお力をお借りし、これからも様々なことに挑戦してまいります。


Well-beingを一緒に
創る仲間を募集しています。
事業連携、取材のご相談など
お気軽にお問い合わせください。